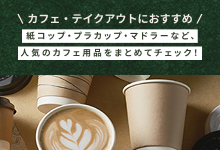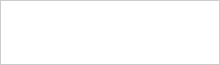「フードロス」と聞くと規模の大きな問題に思えますが、実は私たちの身近なお店でも
日々起こっています。
パッケージプラザ高岡店・富山インター店をご利用頂いているお客様は、飲食店や食品販売を
されている方が多く、毎日の作業のなかでもまだ食べられるのに捨てざるを得ない食品が出て
しまっているのではないでしょうか?
まずはフードロスがどのようにして起こっているのかを考えてみましょう。
【フードロスはどこで起こる?】
「どこでロスが出ているか」を把握する事が第一歩です。
調理前:仕入れ過ぎ
調理中:仕込み過ぎや端材の廃棄
提供中:食べ残しや盛り過ぎ
販売中:期限切れや見た目による売れ残り
●この4つの視点で見ると、改善ポイントが見つけやすくなります。
【すぐに取り入れやすいフードロス対策】
〇 仕入れ・仕込み量を調整する
売れ行きを曜日や天気ごとに記録をしておくと、翌週以降の仕込みに活かすことができます。

〇 在庫を”見える化”する
冷蔵庫に残っている数を貼り出す。
シンプルなアプリで記録するなど小さな工夫で、入れ過ぎを防げます。
〇 期限が迫ったら”お得”に切り替える
値引きシールを貼る、セット販売にする、惣菜や弁当に加工して販売する、などお客様に喜ばれる
形で提供できます。

〇 食べ残しを減らす工夫
小盛りやハーフサイズを選べるメニューを用意するだけでも違います。
さらに、残った料理を持ち帰れる容器を準備し、「お持ち帰りできますよ」と一声添えるのも
効果的です。
POPやポスターを掲示しておいてもいいですね。

〇 余りそうな食材は”おすすめメニューに”
その日のおすすめとして掲示すると、自然に消費でき、お客様にも新鮮な提案になります。
こうした取り組みは特別な設備やコストを必要とせず、すぐに始められる身近な工夫です。
【世界で進化するフードロス対策の最新事例】
一方で、国内外ではフードロスを減らすための最新技術や取り組みも次々と生まれています。
・AIによる需要予測や廃棄分析:仕入や調理の量を自動で最適化
・スマートパッケージ:鮮度をリアルタイムで監視し、食品の保存期間を延ばす技術
・フードシェアアプリ:余った食品を消費者に安く提供する仕組み
・アップサイクル:規格外や副産物を新しい商品に埋まら変わらせる取り組み
このような最先端の技術は、すぐに導入するのは難しくても「未来の方向性」を知る事で
自店の工夫や改善のヒントに繋がります。
【スパックラボもフードロス対策を考えます】
フードロス対策は「完璧にゼロにすること」ではなく、「もったいないを少しでも減らすこと」
から始まります。
仕入れや盛り付けを少し工夫する、余った料理をお客様に持ち帰ってもらうなど、その一つ一つが
立派なフードロス対策です。
そして、パッケージプラザ高岡店内に併設されている、スパックラボでもフードロス対策の提案の
ひとつとして、風味を損なわずに冷凍保存する「特殊冷凍機」の体験をおすすめしています。
「自店の商品を実際に冷凍させ、解凍後の状態を知りたい」や、「冷凍して保存してみたい」など
気軽に試していただけます。
フードロス対策に「特殊冷凍」の提案は㈱スパックのホームページにも掲載しています。
https://spac-package.jp/spac_lab/582/
いろんな角度からいろんな方法でみんなが協力し、できるところから少しでもフードロスを減らせて
いけたらいいのではないかと考えます。